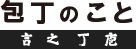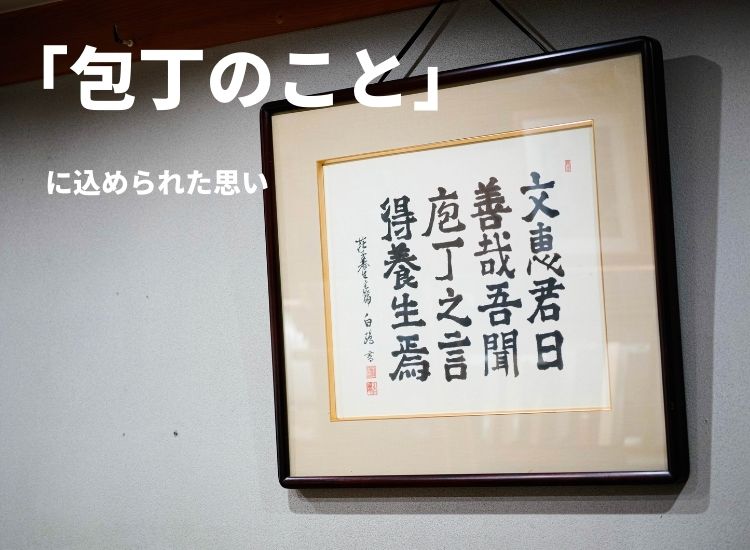本焼き包丁
鋼のみを用いながらも、部位によって異なる性質を生み出す「本焼き」。高い技術と手間をかけて作られる本焼き包丁について、伝統の包丁ブランド、堺一文字光秀が語ります。
本焼きとは
一般的な和包丁は鋼と軟鉄を重ね合わせた鍛接(合わせ)の包丁になり、普段何気なく使用している和包丁はほとんどがこの包丁になります。
ですが、和包丁には鋼のみを鍛造して作った包丁があります。
それを「本焼き」と呼んでいます。
本焼きの由来は、焼入れなどが日本刀と似た製法から造られいることから本焼きと名付けられました。
究極の一本
上の包丁を見ていただくと分かると思いますが、とても高価な包丁です。
同じ鋼材を使用した鍛接(合わせ)包丁と比べて3倍近くも高くなります。
なぜこんなにも高価なのか
それはシンプルに本焼きは造るのがとても難しいからです。
本焼きは硬い鋼一枚で造ることから、鍛造から、焼入れ、さらに刃付けに至るまですべての製作過程で刃が割れてしまうリスクがあるためです。
そのため、職人も刃割れのリスクを考えて一本仕上げるのに、2~3本余分に造る場合もあります。
本焼きの魅力
切れ味の鋭さ
なんと言っても本焼きの一番の魅力は切れ味になります。
鍛接(合わせ)包丁とは違い硬い鋼のみを鍛造するため、しっかりと低温から鋼を叩きのばすので、金属組織が均一に細分化するため、鋼が締まり粘りと硬度のある刃になり鋭い切れ味が出ます。
波紋の美しさ
本焼きは土置きと言う日本刀に似た焼入れをしているため、日本刀のような独特の波紋模様が浮かび上がります。
この波紋模様が切れ味と同じく本焼きの魅力の一つとなっています。
歪みにくい
鍛接(合わせ)包丁は鋼と地金の硬さの違う金属を合わせて造っているため、硬い鋼の方に地金が引っ張れることが多いため、自然と刃が反っていきます。
反面本焼きは鋼のみで造られいることから、鍛接(合わせ)包丁よりも反りが出にくくなっています。
水焼きと油焼き
本焼きを造る製法には大きく二つあり、「水焼き」と「油焼き」の二種類があります。
これは刃の焼入れの時に水使って冷やすか、油を使って冷やすかの違いになります。
水焼き
焼入れを水で冷やすのが水焼きになります。
高温から一気に冷やすため、鋼が締まりより切れ味や刃の持続性が向上します。
ただ急速に温度が下がるのに、鋼が耐え切れずに焼入れの時に刃が良く割れるため、熟練の職人でもとても高度な技術が要求されます。
油焼き
焼入れを油で冷やすのが油焼きになります。
水焼きと比べてゆっくり冷えていくため、焼入れの時の刃割れのリスクが小さくなります。
その分硬さが水焼きより劣るため、切れ味に差が出ると言われています。
ただこれは鋼材の種類や職人の技量でカバー出来るため、一概に水焼きが良いという訳ではありません。
青鋼に関しては油焼きの方が適していると言う職人も居てます。
実は全てが硬いわけではないのです。
本焼きは鋼一枚で造られているため、鍛接(合わせ)包丁とは違い刃全体に硬度があります。
ですが、実は刃全体が同じ硬さがあるわけではないのです。
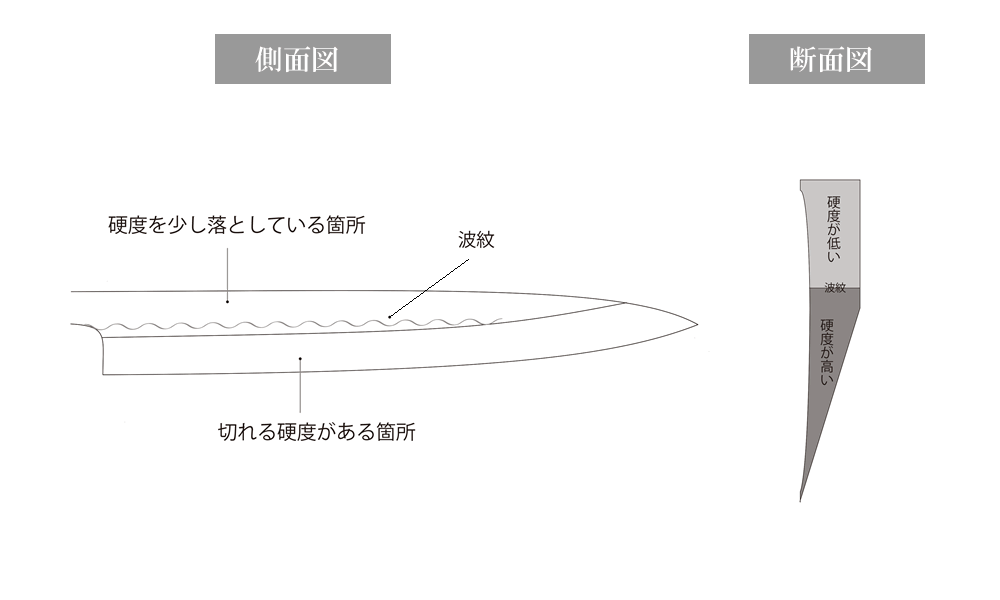
焼入れの工程で本焼きは、平の箇所に土置きをして少し硬度を落として焼入れします。
(これが日本刀に似た製法と言われる所以です。)
なぜこのような焼入れをするかと言いますと、全体に硬度があると少しの衝撃で刃割れが起きたりするため、平の箇所の硬度を少し落とすことでそこがクッション代わりになり、衝撃に強くするためです。
波紋模様

その土置きで焼入れをすることで平と刃で硬度差が生まれ、その硬度差によって刃に独特の波紋模様が浮かび上がります。
この波紋こそが本焼きのもう一つの大きな魅力となっています。
油焼きの方が綺麗な波紋が出ます。
水焼きでも波紋を浮かばせることは出来ますが、実はクッキリとした波紋は油焼きの方が出ると職人は言っています。
そのため波紋の見た目を重視するなら油焼きを選ぶのも選択の一つだと思います。
波紋でこういった物も造れます。
通常の本焼きの波紋は波打った模様が一般的ですが、土置きの方法次第でこのような波紋を浮かびあげることも可能です。

本焼き 富士満月波紋仕上げ
波紋を富士山と満月に似せて作った特別オーダーの本焼きです。
本焼きを使用する上での注意点
刃割れに注意です。
とにもかくにも本焼きはガラス細工のような繊細な包丁です。
そのため鍛接(合わせ)包丁と同じような使い方をしていると刃割れが起こります。
初めて本焼きを購入された方が使用中や研いでいる最中に刃が割れたと言う話をよく聞きます。
それくらい本焼きと言うのは繊細な包丁なので、昔はその技量が伴った料理人のみが使っており、若手料理人のあこがれの包丁でした。
研ぐ時は要注意です。
本焼きを刃割れさせてしまう方で多いのが、研いでいる時です。
鍛接(合わせ)包丁は多少荒い研ぎ方でも問題はありません。
ただ本焼きを同じような研ぎ方をしますと、多くの確立で刃割れします。
そのため本焼きを研ぐ時は常に砥石のセンターで研ぐ意識を持って、あまり指先に力を加え過ぎず角度もブレないように研ぐ技術も必要になってきます。
本焼きと全鋼は違うの?
はい、全く違います。
上記の包丁も鋼(ステンレス系)一枚で造られています。
ですが、こちらは全鋼と呼んでおり本焼きではありません。
それはなぜかと言いますと、鋼を鍛造していないからです。
本焼きは鋼をしっかり叩き鍛造して、焼き入れの際に土置きをして焼き入れをする日本刀に似た製法で造られいるからこそ本焼きと呼ばれています。
材料をプレスで抜き取り、焼き入れをする洋包丁と同じ造りをしているのが全鋼になります。
著者紹介About the author

堺一文字光秀
渡辺 潤
自社ブランド「堺一文字光秀」の販売、包丁研ぎ、銘切りをしており、その視点から感じたことや疑問を皆様にお伝えさせていただきます。
- 監修
- 一文字厨器株式会社(堺一文字光秀)